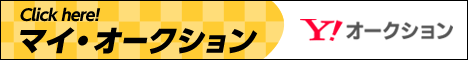|
昭和55年 厚さ約1.2cm 部数は少なそうです。資料用にもいかがでしょうか。
青梅市の町屋 3
第1節 調査の目的
近世には多数の都市が成立しています。 これは近世になって領主の城を中心に城下町が建設された ことや、都市間の物資の移動が活発化するのにともない街道の整備, 海運の発達が促進され,各地に 宿場町 港町が形成されたためです。 城下町, 宿場町, 港町といった近世都市の住民は大部分が武士, 商人、職人であり, 彼らは集住して都市生活を営みました。この点,当時の農民を主体にした村落と は性格をはなはだ異にしています。 都市と農村の分業が確立することによって,わが国の都市数は著 しく増加したわけですが,この近世都市のほとんどが近代以降も存続し、そのいくつかが地方の中枢 都市に発展しています。 そこには,近代の都市へ継承されつつ, 転換が計られていった都市の変遷が あって、それが今日の都市様相にも反映しているのを見ることができます。
都市の歴史すなわち成立 発展における諸様相を追究する場合,経済的な活動は都市の盛衰に密接 に関ってくる基礎的な課題となります。 また都市生活が社会的事象, 文化的事象など多方面にわたっ て展開していることも重要です。さらに個々の都市には,地域的な特徴や独自性も内在しているに違 いありません。 都市住民の集住形態に関して物的な面で注意を向けようとすれば,都市生活者のもっ 身近な街路景観や都市住居も対象となるでありましょう。
町屋 (町家とも書く)とは一般的には,商人・職人などいわゆる町人の都市住居のことで、別な表 現をすれば都市の庶民住居ということになります。 町屋, 農家等を含めて近世的な庶民住居は広く民 家と呼ばれ、現在でも各地に近世に建築された家屋,あるいは明治期に従来の伝統的な手法で建てら れた家屋が残っています。 町屋では京都, 高山, あるいは中仙道の妻籠宿などがとくに有名です。 町 屋は都市発展に伴って農家から派生したものと思われ,両者の居住空間内に土間を配する共通性があ ります。これに対して営業空間としての店(ミセ)の有無といった機能面で相違があり、また都市的 な環境の有無に関ってくる相違も認められます。 たとえば街路に面して多数の屋敷地が配される町屋 敷では,間口が狭く, 奥行が深い短冊形の敷地形が一般的であり, 町屋を建築する際はこのような敷 地の制約が建物配置・平面の前提条件として介在することはほぼ確実でしょう。また外観の意匠的配 慮がいきおい正面すなわち街路側に趣いていることからも、町屋の都市的性格は窺えます。
街路に面して軒を並べた町並において, 町並景観の重要な構成要素が町屋の正面外観であることは 言う迄めないことですが,とくに近世的な町屋が建ち並ぶ場合, 屋根・庇・格子等による類似した正 面外観が続くので,一様で均質な空間印象を感じ取ることができます。 このような町並の中に近代的 な店舗や住宅が混在すると, 近世的なものとは異質な陸屋根風パラペット・ショウウインドゥ,アル ミサッシュ等による形態の相違がはっきり識別されます。 近世においては、町屋の建替えが行われて 町並景観に異質なものを呈することはまずあり得なかったほど一定の質の大工技術が社会の隅々ま で浸透していました。 この手工業的生産段階の木造建築様式が近代以降に継承されなかった事態には, 新材料や新構法の普及、また洋風意匠の導入や商法,住様式の変化が潜んでいます。 したがって都市 景観における近世と近代の混在状況とは,これまでの都市や建築の近代化過程の足跡なのです。
お探しの方、お好きな 方いかがでしょうか。
中古品ですので傷・黄ばみ・破れ・折れ等経年の汚れはあります。表紙小傷、小汚れ。ページ小黄ばみ、軽度の割れあり。ご理解の上、ご購入ください。
もちろん読む分には問題ありません。286932s |

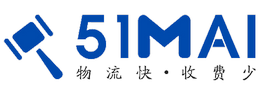






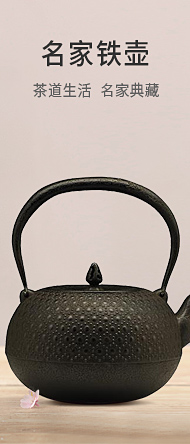


![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-17565180085474zsqwov4468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-175651800872166z2zs84468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-17565180088944if1opp4468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-17565180090612xjlagv4468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-175651800922439m94zg4468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-17565180093926itjjn44468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-1756518009557562so2n4468.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0108/user/b757b8d49135fe1e3e4bc03dfe515eba4a1d1d62ebe06dddec1ab6325deb5c45/i-img1200x674-17565180097244oakisc4468.jpg)