御存知!オジー・オズボーンの大傑作1st「Blizzard of Ozz」 旧規格盤 輸入盤中古でございます。盤共に非常に状態の良い中古でございます。現在では様々なリマスター盤がリリースされておりますが、音質の向上を目指すあまりに低音を利かせ過ぎる、音が角張り過ぎる、制作時に生じたノイズ等を処理する等々が見られ、リミックス感が強いものがございます。またこのOzzy Osbourneカタログの以前のリマスター企画ではテイクを差し替えるのみならず、演奏を差し替えるという暴挙もあり、歴史改竄的なものもございました。こちらはリマスター前でございますが、CD化の上ではそもそも音の調整が成されたもの。何をか言わんや、でございます。 御存知!Ozzy Osbourne(Vo)、名手故Randy Rhoads(G、ex-Quiet Riot)、名手Bob Daisley(B、ex-Widowmaker、Chicken Shack、Rainbow、後にGary Moore、Living Loud他)、名手Lee Kerslake(Ds、ex-Uriah Heep、National Head Band、The Gods他)となります。 また、ゲストとしてDon Airey(Key、ex-Colosseum Ⅱ、当時Rainbow、後にOzzy Osbourne Band、Jethro Tull、Whitesnakeセッション、現Deep Purple)が参加致しております。録音エンジニアとしてかのMax Norman(後にLoudness、Grim Reaper、Megadeth等を手掛ける)が参加となりますが、事実上の共同プロデュースだった模様でございます。 七十年代後半に入り、八十年代という新たな時代に向けて新たな音楽性の模索が始まった音楽シーン。Black Sabbathも御多分に漏れず、名作と呼ばれた「Sabotage」の大作主義志向を反省。(ベスト盤リリースのインターヴァルを経て)コンパクトな意欲作「Technical Ecstasy」を制作。コンパクト指向は同じであったものの、新時代に向けたバンドの音楽性イメージや「メロディにおける色彩感の相違」という大きな隔たりが Iommi/Butlerと Osbourneの間には存在しており、制作は困難を極めます。意欲的であったものの(商業的にも)結果は芳しいものではなく、バンドには不穏な雰囲気が流れます。「Sabotage」制作時から音楽性に不満を感じていたOzzy Osbourneは「色彩感ある音楽がやりたい」とBlack Sabbathを脱退。Tony Iommiが嘗て手掛けた”Necromandus”(作品は当時お蔵入り)のメンバーと合流、音楽性やバンド構想を練る事となります。一方、Black Sabbath側は(かのFleetwood Macを理不尽な扱いの後に解雇された)David Walker(ex-Savoy Brown)を加入させ、新作制作に勤しむ事となります。されど、思う様な結果が得られなかったOzzy Osbourneがバンド復帰を懇願。バンド側はそれを受け入れ復帰させ新作制作に勤しむもののOzzy Osbourneは「他人の曲は歌えない」とDavid Walker在籍時楽曲を拒否。再作曲に再アレンジと紆余曲折の制作の末、新作「Never Say Die !」は完成。デビュー10周年記念と重なり、ツアーへと勤しみますが、新作は不評。おまけに前座に新世代革命児名手Edward Van Halen擁する”Van Halen”を起用するも、その新世代の音楽性にバンドが追いやられる始末。ツアー後は様々な責任問題を巡りバンドは更に不穏な空気が漂う様になり、最後にはOzzy Osbourne解雇となります。解雇されたOzzy Osbourneは以前からの「色彩感ある音楽性」を実現すべく新バンド構想を練るも非常に難航。投げやりになるものの、L.A.での人選で後にVinnie Vincent InvasionやSlaughterで名を成すDana Strumの紹介で名手Randy Rhoadsが加入。(オーディション選考ではなく面接(笑)、初対面・一目で採用(笑)。「ルックスは重要だ」とはOzzy Osbourne談................何だろうねぇ...............)バンドそして音楽性の土台が完成し、嘗てのRainbowの同僚Ronnie James Dioとのバンド構想を練っていた名手Bob Daisleyにアプローチ(ここからRonnie James DioのOzzy Osbourneに対する僻みが始まる感が..............................................)、更には(かのPat Travers Bandの名手Tommy Aldridgeにアプローチするものの契約問題で頓挫した後)そしてバンド内の深刻な対立にあったUriah Heepの名手Lee Kerslakeにアプローチ。双方共に承諾を得て、バンド構想が実現。当初英国のみのものとなるものの契約を締結。本格的に制作が行われる...................という面倒な経緯がございます...................................(そもそもはソロではなく、バンド構想であった感がございます.......................)非常に創造性に富むラインナップという事もあり、楽曲・演奏アンサンブル等非常に充実した内容でございます。(Ozzy Osbourneが何気なく口ずさんだメロディに故Randy Rhoadsが興味を示し作曲が始まり、Bob Daisleyが歌詞を持ってきた云々の逸話も...........................)Quiet Riot在籍時に比べ、故Randy Rhoadsの成長は著しいもの。そもそもQuiet Riotは故Randy Rhoadsのバンド。されど、非常に上手いヴォーカリストであるものの「ワン・スタイル・シンガー」でもあり英国グラム系の音楽性指向の故Kevin DuBrowとRandy Rhoadsの背景にある音楽性がリンクし難い感があり、されど、Ozzy Osbourneが新たに指向する「色彩感ある音楽性」に故Randy Rhoadsのそもそもの音楽性が合致した事が故Randy Rhoadsの才能や技術を強く引き出した感がございます。クラシック・ギター系の技術色が強く、独特の起伏を加えた巧みな演奏スタイルは非常に印象深いもの。但し、同じL.A.のシーンで活動し故Randy Rhoads自身が前座も務めた”Mammoth”改め”Van Halen”の名手革命児Edward Van Halenのスタイルを自ら演奏スタイルに応用した興味深いものでもございます。更にはロック音楽系には非常に稀有な「Bluesの影響が皆無」という才能のギタリストの一人(かの名手Alex Lifesonや名手Robert Fripp、薄いと言えば名手Steve Hackett、名手故Peter Banksや名手Steve Howeくらいでしょうか......)という驚くべき特徴を生かした演奏スタイル、作曲や音楽性を指向。また色彩感が少ないと言われるHM/HR分野ではございますが、ここでは色彩感やポピュラー感を非常に強く打ち出したもの。非常に幅広い音楽性の楽曲が揃い、飽きさせない出来となっております。また、Bob Daisley/Lee Kerslakeのリズム隊も非常に充実したもの。HM/HR界最強のリズム隊の一つではございますが、非常に巧み。非常に起伏に富みスケール感抜群、ハイテク感のみならず変幻自在の感があり、名手故Randy Rhoadsの個性と上手く協調し見事な構築性を見せております。またBob Daisleyは歌詞のみならず作曲にも絡んでおり、リズム面から見た音楽性で貢献していた感がございます(そもそもこのリズム隊自体が作曲に絡む感が,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)。(「Uriah HeepではLee Kerslakeの演奏が他の演奏に非常に大きな影響を与えている」とは某名手系ミュージシャンの御言葉...................)Ozzy Osbourneは自らが望んだ新たな音楽性の実現という事があり非常に意欲的で、ヴォーカルのメロディ面の充実振りには目を見張るものがございます。Black Sabbath隠れ名盤”Technical Ecstasy”以降、模索し続けた色彩感に富んだ音楽性を実現した感がございます。正直巧みなヴォーカリストではございませんが、存在感と応用力は見事なもの。かの名手Rick Wakeman(Yes、ABWH他)が一目置く事が理解出来るものとなっております。元々アカデミック指向な感のある故Randy Rhoads(だから王立音楽院出身名手Don Aireyとウマが合った感......)の意向が強く反映された理路整然とした音楽性の感がございます。故Randy Rhoadsに注目が集まりがちでございますが、スケール感やポピュラー感を生かした楽曲もあり名手リズム隊の有り方が非常な聴きものでございます。またゲストのDon Aireyでございますが.......................そもそもBlack Sabbath”Never Say Die !”に参加した経緯がございますが、何せ王立音楽院出身。アカデミックな背景を持つ技術的にも非常に優れたミュージシャンではございますが、Ozzy Osbourneが高く評価するかのRick Wakeman(Yes、ABWH他)も同学校出身(こちらは中退)という事やそもそもBlack Sabbath自体がかの”Yes”を羨望の眼差しでいた事もあり、非常に理路整然としてアカデミック指向なミュージシャンに対してOzzy Osbourneは非常な敬意を抱く感がございます。そこが起用の理由ではなかろうか?と................................(次作参加のLouis Clarkも同校出身。後々に関わり、バンド結成までOzzy Osbourneに決意させたかの名手Steve Vaiもかのバークレー音楽院出身(秋吉敏子、渡辺貞夫、小曽根真、山中千尋云々と巨匠・名手揃いの母校。かの巨匠Gary Burtonが学長を務めた名門。ジャズ偉人Miles Davisは半日、巨匠Keith Jarrettは三日、名手Tom Scottは一週間で退学でございますが.......)...................................Frank Zappa 出身でもございますが...........)セッション参加とは言えど、アカデミックな背景を持つ事からも(音楽性に自身の意欲が掻き立てられると)バンドの音楽性に介入したがるミュージシャンの感がございます。今作では非常に意欲的な感覚があり、明らかに創作に強く関わっている感のあるパートも存在。非常に興味深いものでございます。公私に渡るDon Aireyの故Randy Rhoadsに対する発言からも非常に実り豊かなセッションであった感があり、その後の正式加入が伺える感がございます..................................(かなりウマが合った模様。Randy Rhoadsが生きていれば、かのPat Metheny/Lyle MaysやSteve Hackett/Nick Magnusの様に長い付き合いになった感がございます........................)今作は事実上Max Normanとの共同プロデュースの模様。音造りも独特なものがあり、正直手造り感がございます。スタジオ制作ならではの加工感があるものでライヴの有り方とギャップが感じられるものでございますが、過度の作り込みをしない所やハードではあってもへヴィさ・暗さを敢えて避けた音造りで非常に興味深いもの。「色彩感のある音楽を造りたい」というBlack Sabbath”Technical Ecstasy”制作時からのOzzy Osbourneの要望が強く反映された感がございます...................................................................................................................バンドは順風満帆。ツアーも大好評で見送られたアメリカでのリリースも決まり、早々とアメリカ進出に向け新作制作が急がれる事となりますが...................................................されど、マネージメントと名手リズム隊とのビジネス解釈(ソロか?バンドか?)が非常に異なるもので、バンド内に不穏な空気が徐々に流れていく事となります.......................................(これが後々の歴史改竄的な再リリースに繋がりますが...................................................) 注:発送方法は変更になる場合がございます。宜しくお願い致します。

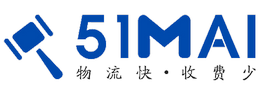






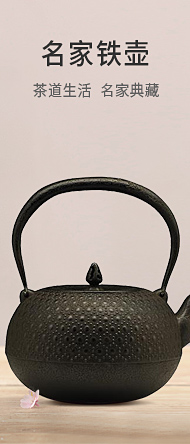

![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0503/users/1a96105645596946c78481f469ec1a41b8bfa8e3/i-img1200x900-1553249673volf3t644000.jpg)



