当前位置:首页
> 首饰、手表
> 妇女装饰品
> 戒指
> 紫翠玉
> 有色寶石
> F4275:交代浴の愛の詩 ウリキリ!色変わりの良いアレキサンドライト0.19ct は熱湯アイスバス? 上質D0.18ct 最高級Pt900無垢リング
- F4275:交代浴の愛の詩 ウリキリ!色変わりの良いアレキサンドライト0.19ct は熱湯アイスバス? 上質D0.18ct 最高級Pt900無垢リング
- 商品编号:j1192543228 【浏览原始网页】
当前价:RMB 1583
加价单位:500日元
出价:33次
直 购 价:RMB 70065.00

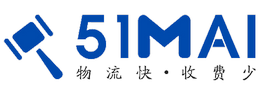








![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0107/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img1200x1200-17524555639281afbaww1265.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0107/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img1200x1200-17524555639510a3bw3s1265.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0107/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img1200x1200-17524555639725cqplyg1265.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0107/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img1200x1200-17531371753379qyxzos40648.jpg)



