本品は、江戸初期〜中期(17世紀後半〜18世紀前半)頃に制作されたと考えられる 古い実用般若面 です。
まず特筆すべきは、現存する文化財級の般若(文化遺産オンライン所載品など)と 明確に同系統の造形 を備えている点です。
■【造形の評価ポイント】
● 眼窩の深さと力強い落とし彫り
古典般若に見られる深い眼窩処理が明確で、単なる観賞用ではなく“実際に舞うための構造”を持ちます。
これは江戸後期以降の簡略面には見られません。
● 鼻梁(びりょう)の美しい通り
細く長く伸びる鼻梁は、江戸初期の上手(じょうて)の特徴。現代面や土産面では再現が難しい骨格です。
● 口元の切れ上がりと強い彫り
口角の鋭い上がり方、上下歯列の深彫りは、室町~江戸初期の古形般若と一致します。
● 頬の張り・側面のライン
側面から見た際の張り・落としのバランスは、文化遺産の“赤鶴作系”の古面と極めて近い作風。
● 角の付け根の自然な造形
木地との一体感が強く、後代の観光向けの付け角とは異なる本格的な処理。
造形だけで判断すれば、50万〜120万級の古格を備えた作品といえます。
■【状態について】
長い年月による彩色剥落があります。
表面の朱・金泥・白色が薄くなっており、これが市場評価に影響しています。
しかしながら、
● 木地の古色
● 裏面の磨耗
● 角周りの摩耗
● 経年の肌合い
これらはむしろ 古面ならではの力強さ・風格を引き出している面 でもあります。
状態のため価格は抑えていますが、
造形の質は文化財級の古面と並べても遜色ありません。
■【総評】
文化遺産オンラインに登録されている数々の江戸初期般若と比較しても、
骨格・彫りの方向性は同一線上 にあります。
状態難はありますが、造形そのものは一級の古面。
古面コレクター、能楽関係者の方には特におすすめします。
時代本物保証。
気になる点はご質問ください。
*説明文の下にも画像がありますのでご覧ください。

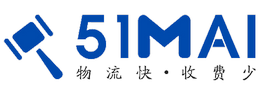






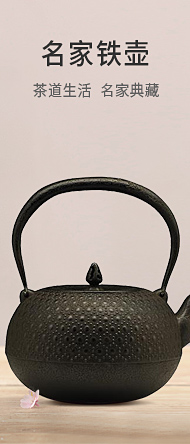


![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-176250958893127hmspb5806.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-17625095888698xufvpg55722.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x1013-17625095888773bhibsb210732.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x1097-17625095890300jaqzts110407.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-176250958894164brmgo3713.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-17625095889410mrhloo164422.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-17625095889699oax0eh231670.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-1762509588975457xpkm135781.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0111/user/ef4cc92cf0aeb2980bb0545ea909da2dbf83b72bb7c339d135ce49f9e1904044/i-img1200x800-17625095890373xy8rei81191.jpg)






