
米国ドレーク社製のアマチュア無線用受信機で、1977年に製造された個体と推定されます。
製造番号は27000番台で後期型です。
以前にもR-4Cを出品しましたが、これは別のものです。
将来の整備や修理などについても対応させていただきますので、ご安心下さい。
その場合、事前にご連絡をいただき、状況やご希望を伺った上での対応になります。
R-4Cには前期型と後期型があります。 前期型はCWフィルタを2本切換え可能(フロントパネルの表示がCW1とCW2のみ)、後期型はCWフィルタを3本切換え可能です(フロントパネルのCWフィルタ切換えが3ポジション)。
そして、後期型の中にも中期型と最終型があります。 主な違いはミキサの真空管が中期型は6HS6、最終型は6EJ7である点です。
尚、CWフィルタ2本を切換え可能な前期型(製造番号が18725番以下のもの)は、
回路構成に起因して近接信号に対するダイナミックレンジが、後期型に比較して20dB程度狭く、
そのため近接信号によるオーバーロードに対しては不利、
と言われている様です。
後期型ではこの弱点が改良されています。
この点を含め、シャーウッドエンジニアリングのロブ・シャーウッド氏が、新発売のR-4Cを160mの実戦で使用したところ、R-4Bで聞こえる信号がR-4Cでは聞こえないことにショックを受け、これを何とかしようという動機で開発を始めた結果が、一連のシャーウッド製R-4C改善モジュールや部品であるのは有名な話です。
R-4CはドレークのR-4シリーズ受信機の四代目モデルで、周波数範囲は実装する水晶振動子の周波数に応じて水晶1枚当たり
1.5MHzから30MHz中の任意の500kHz幅をカバーします。
現状は標準のアマチュアバンド5バンドの水晶5枚を実装していますが、さらに15バンド分の水晶を実装可能です。
1. 整備・アップグレードついて
ダイアルのメカがグラグラであったりツマミがギクシャクと回ってしまうものや、パイロットランプの照明が赤茶けてしまったR-4C、歪やハムやノイズが大きくて濁った音がするR-4C、或いは過去オーナーの整備・調整・レストアによってボコボコにされてしまったR-4Cも見かけられる様ですが、
これはそれらのものと異なり大変に良い状態です。
フロントパネルやダイアルカーソル、化粧ビス類は新品に交換しました。
ケースは塗装工場で再塗装したため、大変良い状態です。
普通の黒色塗装ではなく、ドレーク特有の模様がある焼付塗装です。
プロダクト検波はシャーウッド社のPD-4の特性を改善したものに交換しました。
AM検波は歪が少なく周波数特性が良い専用回路に交換しました。
オーディオアンプもシャーウッド社のAMP-4の特性を改善したものに交換しました。
第三ミキサもシャーウッドのMIX-4の特性を改善したものに交換しました。
電源回路も安定度やリプルリジェクション特性を大幅に改善しました。
尚、半導体回路部電源に12Vの3端子レギュレータを追加する場合は同時にオーディオアンプも消費電力が小さな物(AMP-4C)への変更が必要です。
また、元々の回路ではPTO(VFO)は12V電源ではないため、単純に3端子レギュレータを追加するだけではPTOにとっては意味がありません。
劣化した部品や、今後問題になりそうな部品も交換しました。
同時にドレークの設計上の問題点についても、後述のように多数修正してあります。
整備には12万円程度の費用をかけていますので、通常の完動品を5千円~1万円程度以上で購入するのであれば、この個体の方がお得なのかも知れません。
整備・アップグレードに必要な部品などの例は、
● フロントパネル: ¥9,000
● 真空管: ¥4,000
● ケース塗装: ¥7,000
● プロダクト検波: ¥6,000
● オーディオアンプ: ¥8,000
● AM検波: ¥4,000
● コンデンサ: ¥4,000
● 第三ミキサ: ¥8,000
● 照明フィルム: ¥2,000
● ダイアルカーソル: ¥2,000
● メインダイアル用スカート: ¥3,000
● 化粧ビス、ナット類: ¥1,000
● その他部品: ¥9,000
● ノブ: ¥2,000
部品費合計:¥69,000
整備のベースとなるR-4C:
¥35,000
整備費用: 30時間(1時間当たり¥2,000として
¥60,000)
総計金額: ¥164,000 ( = 69,000 + 35,000 + 60,000)
多数の部品と多くの時間を費やして機械的/電気的にレストアを実施しましたので良好に動作します。
完動品R-4Cをお持ちの方にこそ、その差を実感していただきたい状態に仕上がりました。
電子機器は30年も40年もオーバーホールを実施しませんと特性が劣化して実力の半分も発揮できなくなってしまい、単に真空管や電解コンデンサを交換したり
トリマーやコアを回してSメーターがたくさん振れる様にしただけでは不十分な様です。
傑作モデルと言われる機器類は整備して使用しなければ、とても勿体ないことかも知れません。
パイロットランプを青色LEDに交換する方法もありますが、R-4Cはランプが交流点火のためLEDではチラツキが大きく目が疲れるため、ランプは従来のタイプの新品です。
青色(ドレークブルー)のフィルタは新品に交換しました。

上の写真は、整備・アップグレードに必要となるモジュールです。
何れも一般市販されていないモデルです。
尚、単純にシャーウッド社の市販モジュールを取り付けただけでは、残念ながら当機の様な特性は出ません。
2. SSBの受信状態について
一般に「R-4Cの音色よりも、古い2-Bなどの音色の方が良い」という評価がありますが、その原因である周波数特性が悪い点、
及び歪とノイズ、ハムが多い点を改善しました。
R-4Cのプロダクト検波はゲルマニウムダイオード2本を使った簡易型ですので、平衡型のICを使った米国のシャーウッド社製PD-4の定数を見直したものに交換してあります。 これによりダイナミックレンジと歪が大幅に改善されました。
通常のR-4CはSSB受信時の歪が3%~5%程度と良くありませんが、このR-4Cはプロダクト検波やオーディオアンプを改善したため実測値で0.05%ほどと良好です。
オーディオアンプはシャ-ウッド社のAMP-4を改善したものに交換済みです。
また、AGCを改善したため、特にFast時やアタック時の歪、及びクリックが改善されスムーズになりました。
次の写真はSSBモードでの特性です。
上側右の写真が通常のR-4C(整備を実施して取説に従った調整を実施したもの)の特性、上側左の写真がこのR-4Cの特性です。
3番目の写真は一般にR-4Cに行われている改造(雑誌記事などの平衡型プロダクト検波追加とAFアンプ交換)の実測特性です。
多少の効果が認められますが、まだまだ歪やハムが多いままであることも認められました。
このR-4C以外は音が濁って聞こえます。
歪はプロダクト検波とオーディオアンプが主な原因です。
音の濁りはプロダクト検波とオーディオアンプも原因ですが、PTOの信号が大きなハムを伴い純度が低いことやAGC信号が濁っていることも原因です。
何れも電源の電解コンデンサ劣化などが主な原因ではないので、単純なアンプ交換、プロダクト検波交換、コンデンサ容量増加や3端子レギュレータ追加などでは問題が解決しない様です。
歪もハムも設計起因であるため、多少の個体差はありますがR-4C共通の特性です。
調整や部品交換では問題が改善されず、問題点改善のためには、実装設計と回路設計の変更が必要でした。

このR-4Cは、SSBモードでの歪が0.05%ほどと良好で、ハムも十分に小さな値に改善されていることがわかります。
尚、実験の結果普通のPD-4やAMP-4に交換しただけでは歪は1%以下にならないことがわかり、周波数特性・安定性などの問題も含めてPD-4やAMP-4などの改善や実装変更が必要でした。
オーディオアンプをAMP-4に交換することは特性の向上のみに留まらず、オーディオアンプの大きな発熱をなくすこと、及び電源トランスへの
負担が大幅に減少することによる電源トランスの故障を防止できる効果があります。
下の図でピンク色の線が通常のR-4CのSSBモードでの周波数特性、緑の線がこのR-4C(改善後)の実測特性です。(2-BやR-4より遥かに良い)
オーディオアンプ単体の特性ではなく、検波器からスピーカ端子までの実測特性です。
普通のR-4Cは、SSBモードで低域の3dB落ち周波数が450Hz程度と、あまり音が良くないトランシーバに類似の特性ですが、
このR-4Cは約25Hzに改善しましたので、低域の豊かさと歪感が違います。(低域まで再生可能なちゃんとしたスピーカで聞く必要があります)
20Hzの音を出す必要はない訳ですが、70Hzや100Hz付近を歪なく豊かに再生するためには、この程度の低域特性が望まれます。
 3. AMの受信状態について
3. AMの受信状態について
AMにおいても通常のR-4Cの受信音は歪みぎみであると言われます。
これは、SPR-4やR-4シリーズ全てを含め、検波回路が主な原因であるため、検波回路を改善しました。
具体的には、旧回路(ゲルマニウムダイオード1本による簡易型)を削除し、丸ごと交換(検波基板を追加実装)です。
AM受信では、通常のR-4Cは歪が10%にも及びますが、このR-4Cは0.5%程度の歪で、その差は25dBほどにも達しています。
これは、実際のAM信号をアンテナ端子に入力した時にスピーカ端子に現れた信号の実測データです。
(アンテナ端子からスピーカ端子までの歪特性です)

AMの周波数特性も改善し、通常のR-4Cに比較して、歪が少ないことも合わせて音色に明確な差異が認められる状態になりました。
下の写真は、実際のAM信号をアンテナ端子に入力した場合の、アンテナ端子からスピーカ端子までの周波数特性です。
 4. 感度などについて
4. 感度などについて
下の写真は、レストアが完了した状態で0.1マイクロヴォルトの微弱信号をアンテナ端子に入力した場合の、SSBモードにおけるスピーカ端子での出力信号のスペクトラムです。
大変に素直な特性で、ハムやスプリアス等も見られません。
低域も50Hz以下まで延びているのがわかります。
712Hzにあるのが信号で、20数dB下に広帯域に分布しているのがノイズです。
R-4Cの仕様は入力信号0.25マイクロヴォルトでS/N比10dBですが、
このR-4Cは0.25マイクロヴォルトでの実測値がSSB帯域でS/N比18dBと優秀です。
電源回路や線の引き回し、アースポイント等も修正したため、
音の濁りや歪み感が改善されました。

下側の写真に見られる帯域外の大きなノイズ(画面上ではフィルタ帯域の右側に見えるノイズ)はR-4C固有の特性ですが、これを改善したことでこの個体ではシャーシャー音が目立たなくなりました。
帯域内のノイズ(フロントエンドのノイズフロア)に対して26dB程度低くできました。
このノイズは第三ミキサ部から発生します。
色々なメーカーの真空管を何本も取り替えて最良のものを探す方法もありますが、それでもかなり耳につくレベルです。
これは、第三ミキサの入力回路インピーダンスをとても高く設計し、NF-optからかなり外れたインピーダンスにしてしまっていることも原因の様です。
このR-4Cは、第三ミキサを平衡型ミキサ(シャーウッド社のMIX-4を改善したもの)に変更して、真空管式に比較して10dB~20dB以上のノイズ低減ができたと同時に、フリッカノイズや第3IFへの誘導ノイズも低減することができました。
誘導ノイズは、例えばインバータ式の蛍光灯を近隣で動作させた際にノイズがIF回路に飛び込んで、「チュワー」といった感じのノイズが受信機のスピーカから出てしまう現象です。
ドレークはシールド板を追加することによってこれを低減する手法を取ったと考えられますが、第三ミキサ部のインピーダンスが高く設計されているため、有意に誘導を受けやすい様に思われます。
また、オリジナルの真空管式第三ミキサは平衡型でないため、このままでは第三ローカルオシレータの信号が第二IFに飛び込んで、最終的に50kHz信号となって検波段に到達する問題もありますが、今回のアップグレードでこの点も解決しました。
同時に、第三ミキサのインピーダンスを低く設計することで、IFフィルタ前からの信号の飛び付き(通り抜け)も改善できています。
R-4Cはフロントエンドが大変に優れていますので、その部分はほぼオリジナルのままとしてあります。
第三ミキサ、プロダクト検波、AM検波、AGC、オーディオアンプ、電源部には改善の余地(問題)もあるため、それらの問題を改善(ほぼ交換)しました。
また、PTOのハム問題も改善してあります。
音の濁りや歪み感が大きく改善され、またヘッドホンでもハムやノイズが耳につかなくなりました。
落札者には取説の電子ファイル(CD)を差し上げます。

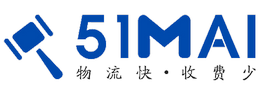






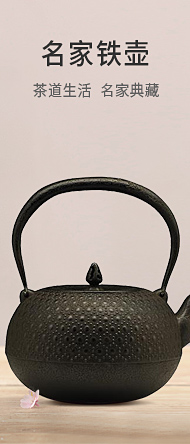


![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0109/user/a071f28c0fc19f0fd0eac28a93683ee7e2303ce5babfb64e673ec28762f0bbdc/i-img600x555-1757855100973191g2bfgs8.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0109/user/a071f28c0fc19f0fd0eac28a93683ee7e2303ce5babfb64e673ec28762f0bbdc/i-img586x600-1757855100973212lras2s8.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0109/user/a071f28c0fc19f0fd0eac28a93683ee7e2303ce5babfb64e673ec28762f0bbdc/i-img600x440-1757855100973221tesyog8.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0109/user/a071f28c0fc19f0fd0eac28a93683ee7e2303ce5babfb64e673ec28762f0bbdc/i-img443x600-1757855100973230fsesog8.jpg)










