当前位置:首页
> 美术品
> 雕刻
> 爱好、文化
> 东方雕刻
> 其他
> D1685 珠玉之珍(しゅぎょくのちん)石黒光南 光と影が織りなす純金の霰 100g 伝統工芸の極致 美術品 幅47.0mm×高52.0mm
- D1685 珠玉之珍(しゅぎょくのちん)石黒光南 光と影が織りなす純金の霰 100g 伝統工芸の極致 美術品 幅47.0mm×高52.0mm
- 商品编号:u1186146214 【浏览原始网页】
当前价:RMB 155700
加价单位:1000日元
出价:0次

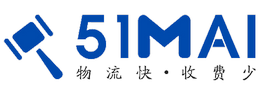








![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img600x600-17480771249712xy7nri84091.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img600x600-174807712497936z6avq84091.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img600x600-17480771249856yhcy8h84091.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img600x600-17480771249937tfaajm84091.jpg)
![{$data['title']拍卖](http://yahooimg2.ymibuy.cn/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0105/user/aa3084801733f53c73d68be93f6f22624b81988d814d4713a023b528455c82b2/i-img400x400-17480771249972dgpcvr84091.jpg)



